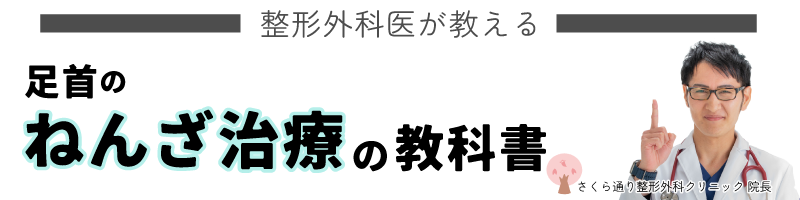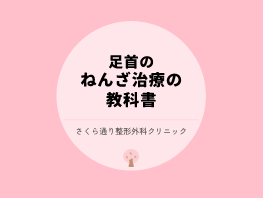【なぜチアリーディングで足首の捻挫が多いのか?】
診察室では、「トータッチの着地でグニッと…」「スタントで体勢を崩して…」というお話をよく伺います。 チアはジャンプ・タンブリング・スタント・ダンスを組み合わせる競技。高い跳躍と素早い方向転換、そして“着地の精度”が足首に大きな負荷をかけます。 ここでは、実際のチアの動きを例に、「なぜ捻挫が起きやすいのか」「どう予防・対処すべきか」をわかりやすく解説します。
ジャンプの着地で「ズシッ→グニッ」
「トータッチの着地で、つま先から外に倒れてしまって…」 ジャンプ種目(トータッチ、ハードラー、ハークなど)は、空中での股関節外転・膝伸展後に、短時間で真下に減速します。 このとき足関節の背屈(曲がり)不足や体幹のブレがあると、外側靱帯にひねり(内反)が集中しやすくなります。マットの継ぎ目・硬さのムラも一因です。
タンブリングで「着地が流れて外側へ」
「バク転→バック宙の流れで、最後の着地が流れて外側に体重が乗りました」 連続技は回転慣性が残り、最後の減速〜静止で足首にピーク負荷がかかります。 手首・肘・肩の疲労から着手が浅くなる→回転が崩れて着地がズレる→足首で無理に帳尻…という連鎖も典型です。
スタントで「支える側のひねり」
「トップが一瞬バランスを崩し、ベースの足が外側に持っていかれて…」 スタントは荷重の微妙な揺れに対して、ベース・スポッターが片脚で踏ん張る場面が多く、外側靱帯の内反捻挫が起きやすくなります。床材の滑りやすさ・シューズのグリップも影響します。
「慣れ」と「疲労」で注意力が落ちる
「いつも通りのルーティンで、最後の決めで踏み外しました」 練習の終盤や本番の連日出演では、集中力低下・反応遅延・着地衝撃の増大が重なり、捻挫リスクが上がります。
テーピングやブレースを外した日に…
「痛みがなかったので今日は巻かずに練習したら再発しました」 足首捻挫は“再発しやすい”ケガ。不安が残る期間は、テーピングやブレース(足首サポーター)の併用が有効です。
【リハビリ】マットに安心して戻るための回復ステップ
焦って復帰すると、また同じ場所を痛めることが少なくありません。 “痛くない”ではなく“着地で踏ん張れる足首”をゴールに、段階的に戻しましょう。
炎症期(受傷直後〜3日)
最優先は腫れと痛みを抑えること。
- 冷却:氷で15〜20分、1日数回(直接皮膚に当てない)
- 圧迫:弾性包帯・サポーターで軽く圧迫
- 挙上:心臓より高く上げて安静
- 荷重は痛みの出ない範囲で:松葉杖やブーツが必要な場合も
- チームメイト・コーチとつながる:ケガをすると気持ちが落ちやすい時期。スタンツの組(ベース/トップ/スポッター)やコーチに現状を共有し、代役や当面の役割(撮影・カウント出し・安全チェックなど)を決めておくと「置いていかれる不安」がグッと減ります。練習動画を共有してもらってイメトレするのも◎
「動ける=大丈夫」ではありません。腫れ・熱感が強い間は無理を避けます。
修復期(3日〜2週間)
痛みが和らいだら、可動域と筋の再教育を始めます。いきなり全力はNG。
- 可動域:足首ゆっくり回し、アルファベット書き、タオルギャザー
- 筋力:チューブで外反/背屈、両脚カーフレイズ(床)
- 荷重:痛みなく平地10〜15分歩行
- 体幹・股関節:プランク、クラムシェルで着地安定性を作る
- チーム参加を続ける:この時期は役割を“見る・伝える”にシフト。カウント出し、動画撮影、モーションの手先だけの確認など、痛みゼロの範囲で関わりを保つとメンタルが安定し、復帰後の連携もスムーズです。
“痛みがぶり返さない範囲”が合図。翌日に腫れ・痛みが増える負荷は早すぎます。
回復期(2〜6週間)
チア特有の動きへ段階的に復帰します。
- バランス:片脚立ち(目を閉じて10秒)→不安定面(バランスディスク)
- 着地技術:“静かに着地”ドリル(膝・股関節を使ってソフトに)
- ホップ系:前方・左右ホップ、ライン越えホップ
- ラダードリル:インアウト、サイドステップ、急停止→方向転換
- チア動作:小さめジャンプ→通常ジャンプ、短いタンブリングから再開
- スタント:低い段階(延長・ハーフ)→高い段階へ。必ずスポッター配置
調子が良い日ほど“あえて一段階下げる”慎重さが再発予防になります。
復帰の判断基準(目安)
以下が痛み・不安なくできれば、段階的な練習復帰のサインです。
- 片脚ホップ10回×左右(着地が静か、ぐらつき最小)
- 30秒の片脚バランス(目つぶり)が安定
- トータッチ10回の連続着地でフォームが崩れない
- 短いタンブリング(例:ラウンドオフ→バク転)を痛みなく2〜3セット
- スタントの基本段階を5回連続で安全に実施(スポッター付き)
- スパイク/チアシューズでの10分ランが不安なく可能
迷ったら、テーピングやブレースを併用し、練習強度は“7割”から戻しましょう。
【再発予防】チアに必要な「3つの備え」
① 道具と環境を整える
- シューズ:サイズ・フィット・グリップを再確認(紐の緩みも要注意)
- マット:継ぎ目・段差・滑りやすさを事前チェック
- ブレース/テーピング:不安がある間は併用を。遠征用にも常備
- インソール:土踏まずのサポートで足首のブレ低減に有効
② 判断力・チームワークも“安全技術”
- 着地は“静かに”:音が大きい=減速不足のサイン
- 合図の徹底:スタントの上げ下げ・解除を声で同期
- 疲労を感じたら一度止まる:連続本番や長時間練習は特に
- ルーティンの最後こそ集中:“慣れた動き”に事故が潜みます
③ “育てて守る”足首づくり
- ふくらはぎ・腓骨筋強化:段差カーフレイズ、外反(エバージョン)トレ
- 股関節安定化:クラムシェル、モンスタウォーク(膝が内に入らない)
- 可動域:足関節背屈のストレッチ(壁ドリル、アキレス腱)
- 実戦ドリル:階段・坂道の昇降、方向転換の減速トレ
コツコツ続ける“足首を育てる”意識が、演技のキレと安全性を両立させます。
よくある質問(Q&A)
- Q. 湿布だけで治りますか?
→ 痛みが軽ければ和らぎますが、可動域・筋力・バランスの回復がないと再発しやすくなります。 - Q. 受診の目安は?
→ 強い腫れ・内出血・体重をかけられない・骨の圧痛があれば早めに受診を。骨折や重度靱帯損傷の可能性があります。 - Q. いつから本格復帰できますか?
→ 損傷度や個人差で変わります。上の復帰基準をクリアし、主治医の先生と相談して段階的に戻しましょう。
最後に|「また笑顔でステージへ」
ケガは悔しいもの。でも、着地の質・体幹の安定・チームの連携を見直すきっかけにもなります。 焦らず、一歩ずつ。“踏ん張れる足首”を取り戻せば、必ずまた自信を持ってステージに立てます。 私たちも、あなたの安全で美しいパフォーマンスを全力で応援しています。