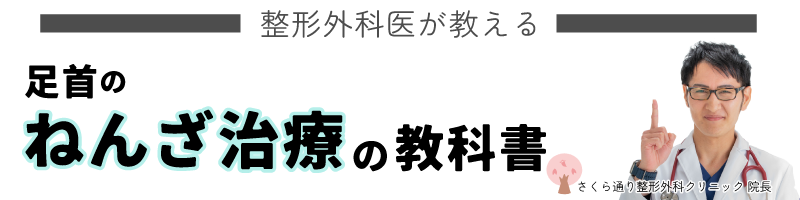【その“急ターン”危険です】足首にかかる意外な負担
診察室では「歩いているときに知り合いを見つけて急に方向を変えたら、足首にグキッと…」というケースも少なくありません。 スポーツ中の動きだけでなく、普段の何気ない日常動作の中にも、足首を痛める“落とし穴”は潜んでいます。 今回は、急な方向転換によって足首をひねってしまう原因や背景、注意点を詳しくご紹介します。

曲がろうとした瞬間に「グキッ」…
「道を歩いていたとき、たまたま知り合いを見かけて“あっ!”と思って急に方向を変えた瞬間、足首に“グキッ”という衝撃が。最初は違和感程度だったけれど、時間が経つにつれてじわじわ痛くなり、夜には腫れてきました」
こういったエピソードは、決して珍しいものではありません。
足をしっかり地面について体重が乗っている状態で急に方向を変えると、足首にねじれの力が強く加わり、内側(内反方向)へ過度にひねられることで靭帯を損傷してしまうことがあります。
特に、急いでいたり、不意を突かれるような動作ではバランスが取りにくく、思わぬ角度で足をひねってしまうのです。
一見「大したことのない動き」に見えても、体重の乗った足で急旋回する動きは、足首にとっては大きな負担になるのです。

日常生活でも起こりうるケガ
足首の捻挫というと、スポーツ中のケガというイメージが強いかもしれませんが、実際にはこうした**日常生活の中の何気ない動き**で起こることが多くあります。
たとえば、
・狭い通路で急に方向転換をしたとき
・買い物中に後ろから名前を呼ばれて振り返ったとき
・人混みを避けようとして咄嗟に方向を変えたとき
など、特別な動きではないからこそ油断しがちで、足の準備が整っていないまま無理な負荷をかけてしまうのです。
靴のグリップが効きすぎていたり、逆に滑りやすい床だったりする場合も、足首の自由がきかず、捻挫しやすくなります。
「急に動く」「ひねる」動作は、日常のあらゆる場面で潜んでいるリスクなのです。
筋力とバランス感覚の低下が拍車をかける
年齢を重ねると、知らないうちに足首を支える筋力や、姿勢をコントロールするバランス感覚が衰えてきます。 特に40代以降では、「以前は何ともなかった動作が、思わぬケガにつながった」という声をよく耳にします。
・足の指先まで力が入らない
・一歩目の踏み出しでふらつく
・段差でバランスを崩しやすくなった
こうした変化がある方は、身体が不意の動きに対応しづらくなっているサインかもしれません。
急な方向転換や反射的な動作の前に、こうした衰えが関与していることも多く、特に注意が必要です。
急なひねりを避けるためにできること
日常の中で足首を守るためには、まず**「急な動きが起きそうな場面」に気づく意識**を持つことが重要です。
・人混みでは余裕を持って歩く
・振り返るときは必ず足も一緒に向ける
・走らなくても済むような時間の余裕をつくる
また、足首まわりの筋肉を鍛えるカーフレイズや、バランス力を高める片足立ちなど、日々の簡単な運動でもケガの予防に大きく役立ちます。
何気ない日常の動きこそ、丁寧に行うことが大切です。
【リハビリ】日常生活に戻るための3ステップ
足首を捻挫してしまったとき、「痛みが引いた=治った」と思って動いてしまう方は少なくありません。ですが、実はそこからが大切な時間です。 無理をして再びひねってしまうと、症状が慢性化することもあるため、**段階的に回復を進めることが、安心して日常生活に戻るためのカギ**となります。ここでは、リハビリの基本となる3つのステップをご紹介します。
炎症期(受傷直後〜3日程度)
受傷から数日間は、足首が腫れて熱を持ち、痛みも強い状態です。この時期に大切なのは、**腫れや炎症をこれ以上悪化させないこと**。刺激を避け、患部を落ち着かせましょう。
- RICE処置を徹底 安静(Rest)、冷却(Ice)、圧迫(Compression)、挙上(Elevation)を正しく行うことで、炎症や腫れを最小限に抑えることができます。氷水をビニール袋に入れ、タオル越しに15〜20分冷やすのがポイントです。
- 無理な移動や入浴は控える 痛みが少し引いても、長時間歩いたり、湯船に浸かることで血流が良くなり、腫れが悪化することも。必要最低限の移動にとどめ、シャワーで済ませるようにしましょう。
この時期は「何もできない」と感じるかもしれませんが、身体を休めることも大切な治療のひとつ。
溜まっていた本を読んだり、録画していたドラマをゆっくり観るなど、少し気を緩める時間と考えてもいいかもしれません。

修復期(3日〜2週間程度)
腫れや痛みが和らいできたら、今度は**足首を少しずつ動かして、機能を取り戻していく時期**です。 動かさずに放置していると、関節が固まってしまい、回復後の動きに支障をきたすことがあります。
- 可動域と筋力の回復を意識 足首を軽く回したり、床に置いたタオルを足の指で手繰り寄せる「タオルギャザー」、チューブを使った足首の抵抗運動などを取り入れましょう。無理のない範囲で、少しずつ負荷をかけていくのがコツです。
- 短い距離の歩行や軽いストレッチ 家の中で数歩だけ歩いてみたり、ふくらはぎを軽く伸ばすなど、日常動作の中でも自然にリハビリができます。違和感がなければ、朝の支度の合間やテレビを観ながらの“ながら運動”でも十分です。
「昨日よりスムーズに動かせたかも」「今日は少し長く歩けた」――そんな小さな変化に気づけるようになると、心にも余裕が生まれてきます。
回復期(2週間〜4週間以降)
見た目の腫れが落ち着き、痛みもほとんど気にならなくなってきた時期です。 ただし、ここで元通りに戻ったと安心してしまうと、再発する可能性が高くなります。**足首の安定性とバランス機能をしっかり整えることが“仕上げ”の段階**です。
- 段差を使ったカーフレイズ つま先立ちでかかとをゆっくり上下させるトレーニングです。ふくらはぎや足首まわりの筋力を鍛え、踏ん張る力を育てます。洗面所で歯を磨きながら行うなど、生活の中に自然と取り入れると継続しやすくなります。
- 片足立ち・バランストレーニング 受傷側の足で10秒間静止することから始め、徐々に時間を伸ばしていきます。キッチンマットや柔らかい床の上で行うと、足裏の感覚やバランス能力をより効果的に刺激できます。目を閉じることで難易度が上がり、体幹の強化にもつながります。
この時期は、「以前より足に力が入る」「不安なく歩けるようになった」など、目に見える回復が実感できるようになります。
焦らず、自分のペースでじっくり整えていくことが、再発を防ぐいちばんの近道です。
リハビリは“やったほうがいい”ではなく、“やらなければいけない”大切なステップです。
適切なリハビリを積み重ねることで、ケガをする前よりも強く、安定した足首をつくることができます。
今日のひと工夫が、明日の安心につながる――その気持ちを忘れずに、無理なく続けていきましょう。
【再発予防】足首を守る3つの準備
足首の捻挫は、一度経験すると「クセになる」と言われるように、再発しやすいケガのひとつです。 特に、靭帯が緩んだまま回復を終えると、ちょっとした段差や何気ない動作で再び足首をひねってしまうリスクが高まります。 そうならないために、普段の生活の中で意識しておきたい3つのポイントをご紹介します。
① 足元の環境確認
まず心がけたいのは、**「足元を確認する習慣」**を持つことです。少し意識を変えるだけで、防げるケガはたくさんあります。
- 外出先では段差や滑りやすい床に注意 駅の階段、コンビニの入口、雨の日のタイルなど、足元が不安定な場所は意外と多くあります。足を踏み出す前に、「ここは滑りやすいかも」と目で確認するクセをつけましょう。
- 暗がりではライトを活用する 夜道や玄関など、視界が悪い場所ではつまずきやすくなります。スマートフォンのライトやセンサーライトを上手に使い、視認性を確保しましょう。
- 自宅の中も見直してみる めくれたカーペットや段差のある廊下、濡れた玄関マットなど、自宅にも転倒リスクは潜んでいます。普段歩くルートを一度見直して、危ない場所がないか確認しておくと安心です。
② 靴の選び方を見直す
足首の安定感は、履いている靴によって大きく左右されます。普段履き慣れている靴でも、実は足を守れていないこともあります。
- ヒールや厚底靴は慎重に 高さがある靴は重心が不安定になりやすく、ちょっとした段差や傾きでバランスを崩しやすくなります。特に階段や長時間の外出時は、ヒールの使用を避けるのがベターです。
- かかとのしっかりした靴を選ぶ 足首をしっかりホールドしてくれる靴は、ねじれやブレを防いでくれます。スリッポンやサンダルのように固定力が弱い靴は、つまずきやすいため注意が必要です。
- 靴底のグリップをチェック 滑りやすいソールは、特に雨の日や濡れた床で危険です。凹凸のある靴底を選び、すり減ってきたら早めに買い替えることも大切です。
③ 足首のトレーニング
靭帯を支える筋肉や神経の反応力を鍛えることで、足首の再発リスクを下げることができます。無理のない範囲で、日常生活に取り入れられる運動を続けていきましょう。
- カーフレイズ(つま先立ち運動) 段差や階段の縁に立ち、かかとをゆっくり上下させる動きです。ふくらはぎと足首周囲の筋肉をしっかり使うことで、着地時の安定性が高まります。歯磨き中などの“ながら運動”にもおすすめです。
- タオルギャザー 足の指で床のタオルをたぐり寄せる運動です。足裏の細かな筋肉を鍛えることで、踏ん張る力や姿勢の安定性が向上します。
- 片足立ちバランストレーニング 片足で静止する練習を毎日少しずつ。最初は10秒から始め、慣れてきたら目を閉じたり、柔らかい床で行ってみましょう。足首まわりの感覚を磨くことにもつながります。
足首の再発予防は、「特別なトレーニングをすること」よりも、普段の動作にどれだけ気を配れるかが大きなポイントです。
一度ケガをしたからこそ、今の自分の身体と向き合う良いきっかけにもなります。今日からできる小さな積み重ねが、明日のケガを防いでくれるはずです。
無理なく、自分のペースで取り組んでいきましょう。
最後に|「“急ターン”は思わぬ落とし穴です」
ふと誰かに呼ばれたとき、急いで方向を変えたとき――日常の何気ない“急ターン”が、足首に大きな負担をかけていることは意外と知られていません。 一瞬のねじれが靭帯を傷つけ、気づかぬうちに足首の不安定さにつながっているケースもあります。
スポーツのように派手な動きでなくても、体重がかかった状態での方向転換は十分に危険なのです。
だからこそ、普段から足首を支える筋力やバランスを整え、安定した動作を習慣づけておくことが大切です。
「ちょっと動いただけなのに…」と後悔しないためにも、自分の動きのクセに気づき、足元を守る意識を持つこと。
その積み重ねが、ケガの予防にも、未来の健康にもつながっていきます。